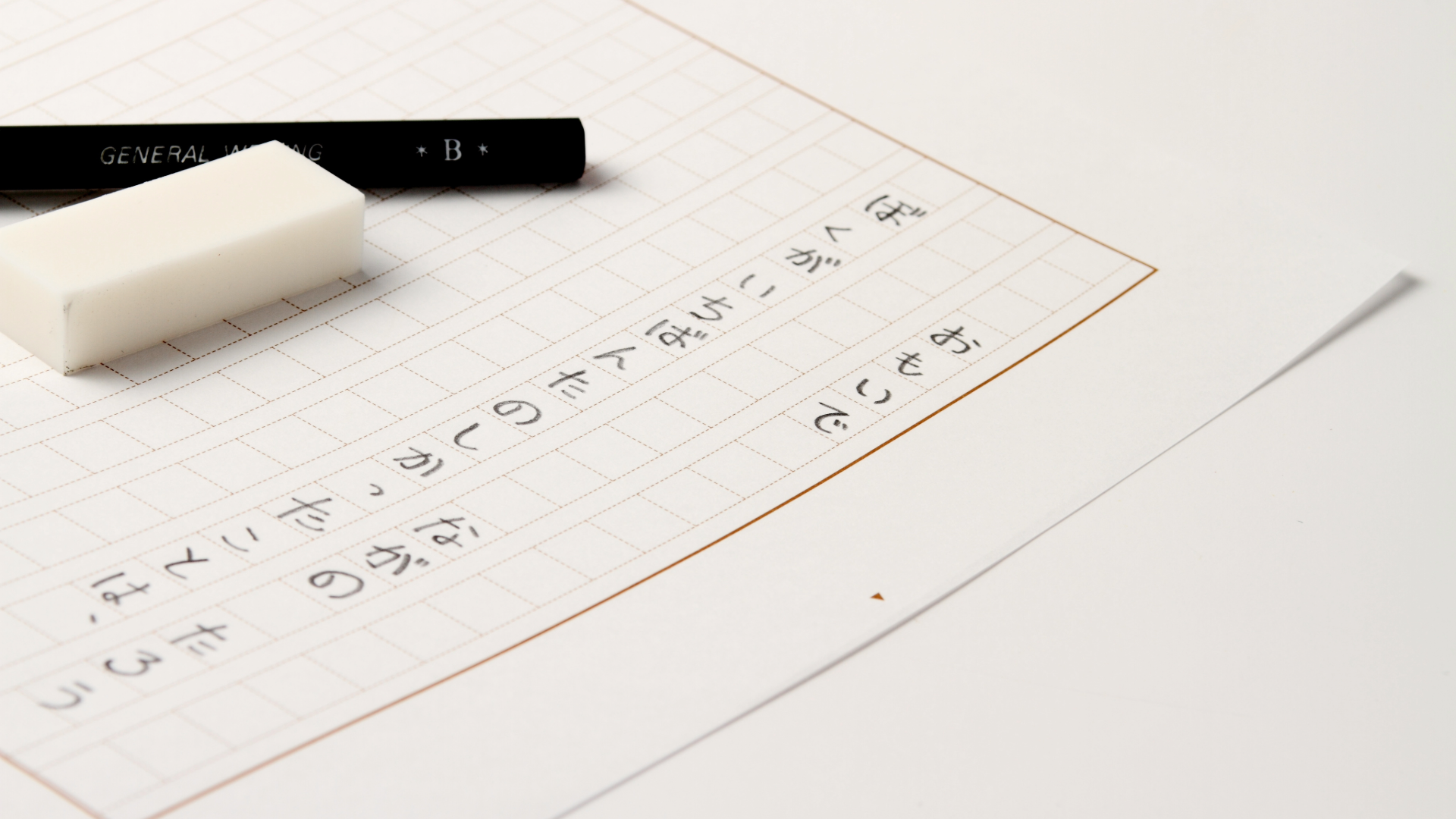事件報道などで、被疑者が小学生や中学生の頃に書いた「卒業文集」がテレビやネットニュースで紹介される場面を目にしたことがある方も多いのではないでしょうか。
文集の実物をカメラで映したり、ナレーション付きで読み上げたりする報道が多く見られます。
しかし、そもそもこのような卒業文集の報道は、著作権の面から見て問題はないのでしょうか?
今回は、卒業文集と著作権の関係について、報道との関係を軸に考えてみます。
著作物としての「卒業文集」
まず前提として、卒業文集に掲載された文章は、多くの場合「著作物」に該当すると考えられます。
著作権法(以下「法」)上の「著作物」とは、思想または感情を創作的に表現したもの(法2条1項1号)であるため、たとえ子どもが書いた短い文章であっても、この定義に該当すれば著作物であるとして著作権が発生します。
一般的に、最初から最後までありきたりな表現だけで記されているということはなく、それを書いた者の「思想または感情」が「創作的に表現」されている場合がほとんどだと思いますので、卒業文集に書かれた作文は著作物として保護される可能性が高いと考えられます。
問題となる著作権は「公表権」と「公衆送信権」
では卒業文集に掲載された作文が著作物であるとした場合、どのような権利が関係してくるでしょうか。
公表権(法18条)
公表権とは、「著作物を公表するかどうか、公表する場合はいつ・どのような方法で行うか」を著作者が決めることができる権利です。
(公表権)
第十八条 著作者は、その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において同じ。)を公衆に提供し、又は提示する権利を有する。当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても、同様とする。
(2項以下省略)
卒業文集のイメージとしては、広く世間一般に公開されるものではなく、特定の学校の特定年度の卒業生だけに配布されるものであるため、卒業生自身としても「公表した」とは考えていないかもしれません。
ここで「公表」とは何かを考えますと、通常の日本語としての意味ではなく、法律上の定義では「発行」されたときに公表されたものとして扱われます(法4条1項)。
そして、「発行」とは、「その性質に応じ公衆の要求を満たすことができる相当程度の部数の複製物が作成され、頒布された」ことを指すと定義されています(法3条1項)。
これを卒業文集に当てはめて考えますと、「公衆」とは特定多数も含むとされていますので(法2条5項)、卒業文集という著作物の性質(作成・頒布する目的や頒布対象など)からすると、その学校のその年度の卒業生全員(公衆=特定多数)に頒布されるのであれば「公衆の要求を満たすことができる」部数が頒布されたと考えることができ、結果として「公表された」といえます。
実際にこの点について判断されたのが、いわゆる「中田英寿事件」(東京地判H12.2.29)で、学年文集に掲載された詩について、その年度の卒業生と教諭に対して合計300部以上が配布されており、またその詩を書いた者も学年文集に掲載されることを承諾していたものであるため、その詩は公表されたものであると判断しています。
したがって、卒業文集の内容を報道で取り上げること自体が公表権の侵害になる可能性は低いと考えられます。
ただ、たとえば卒業生が数人程度といった非常に少ない学校の卒業文集だった場合は「発行」されたといえるかは判断が難しいようにも感じます。
公衆送信権(法23条)
一方で注意が必要なのが、公衆送信権です。
テレビ放送やインターネット配信など、不特定多数に向けて著作物を送信する行為は公衆送信に該当します。
報道番組で卒業文集を映し出すことは、この「公衆送信」に当たるため、原則として著作権者の許諾が必要になります。
報道のための例外規定
このように公衆送信については権利者の許諾なく行うことは原則としてできませんが、報道目的での利用には一定の「例外」が認められています。
それが法41条の「時事の事件の報道のための利用」という権利制限規定です。
(時事の事件の報道のための利用)
第四十一条 写真、映画、放送その他の方法によつて時事の事件を報道する場合には、当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著作物は、報道の目的上正当な範囲内において、複製し、及び当該事件の報道に伴つて利用することができる。
この規定により、「当該事件(=時事の事件)を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著作物」については報道のために利用することができるとされています。
この規定により、たとえば美術館から盗まれたとされる絵画を放送することもできますし、地震災害の様子を被災地に住む人が撮影しSNSに投稿した写真や動画を、その撮影者の許諾を得ることなく放送することができます。
対象の著作物なのか?
ただ、盗まれた絵画や被災写真といった先述の例はいずれも「事件を構成し、または事件の過程において見られる」ものであるといえますが、たとえば殺人事件の被疑者(容疑者)が小学生の頃に書いた文章は、法41条により利用できる著作物であるといえるのでしょうか。
その文章に殺人事件のことを書いていたのであれば別ですが、通常は「殺人事件」と「小学生時代に書いた文章」の関連性は低く、「当該事件(=殺人事件)を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著作物」といえるかは一概には判断できず、ケースバイケースであるように感じます。
また、仮に報道利用できる対象の著作物だったとしても、その利用が法41条にも明示されている「報道の目的上正当な範囲内」か否かについても、常に留意する必要があります。
「引用」として認められる可能性も
仮に先述の法41条の要件を満たさない場合でも、法32条の「引用」として正当化される余地があります。
引用が成立するには、主に次のような条件を満たす必要があります:
- 引用部分が主従関係で「従」となっていること
- 出典を明示していること
- 必然性があること(報道における説明・論評の根拠など)
- 改変しないこと
卒業文集の一節を、被疑者の人となりや過去の行動を説明する目的で、必要最小限の範囲で紹介し、出典も明示していれば、引用として認められる可能性はあります。
ただし、全文を読み上げたり、映像で文集を詳細に映したりするような過剰な使用は、「引用の範囲を超えている」と判断される恐れもあるのではないでしょうか。
文集の報道には慎重な判断が必要
卒業文集に掲載している文章は、書いた本人に著作権がある著作物であり、その内容をテレビなどで取り上げる場合は、公衆送信権の問題が生じます。
ただし、報道の目的であれば、法41条や32条に基づき、一定の条件のもとで利用できる可能性があります。
とはいえ、どこまでが「報道のために正当」と言えるのか、その判断は一律にはできません。
文集の内容を報道する意味や意義はあるのか、報道機関は社会的責任を負う立場として、本人の権利と報道の自由のバランスに配慮した運用が求められのではないか、と筆者は考えます。