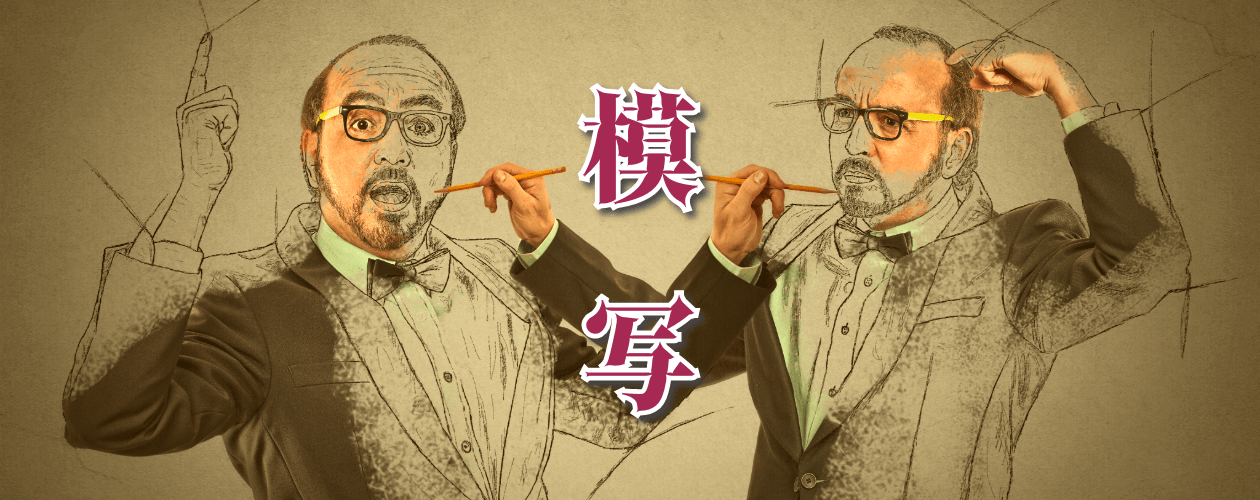画家やイラストレーターだけでなく、絵を描くことが好きな人にとっては、技術向上のために避けては通れない「模写」。
この模写という行為に関して、著作権法(以下「法」)ではどのように取り扱うのかについて考えてみたいと思います。
先に結論を言ってしまうと、「許諾がある場合を除き、模写をすること自体は作者の権利を侵害しないが、ネットにアップ等してしまうと複製権侵害に該当する」ことになります。
模写とは?
法に当てはめて考える際に、まずそもそも「模写」というのは何か、について考えてみようと思います。
「模写」という言葉について、広辞苑第七版では次のように説明されています。
”実物そっくりにまねてうつすこと。また、そのうつしとったもの。「壁画を―する」”
国語的な意味では上記かと思いますが、これを美術・絵画分野に限って考えますと、”実物”というのは他人の作品であることが多いかと思いますので、「他人の作品を忠実に真似して写し描くこと」という国語的な意味に加えて、「写し描く行為によってその作品に込めた作者の意図や技術などを理解し、また体感するための方法」であると言えると思います。
英語では模写を reproduction と訳すようですが、類似する単語の copy に対して、特に絵画分野に限った copy を reproduction と言うようです。
よって、模写という行為が、新たな作品を創作することを目的として行われるものではないという点から考えても、copy と同様に「複製」行為と考えても良いかと思います。
模写できるのは著作者だけ、が原則
模写が複製行為であると考えた場合、その複製行為は誰でも自由に行うことができるものでしょうか?
複製である以上、ここで考えなければならないのが、法21条で定められる「複製権」ですので、実際に条文を見てみましょう。
(複製権)
第二十一条 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
たったこれだけです。とても短くシンプルで、わかりやすいですね。
”専有”というのは、他の言葉でいえば”独占”とほぼ同じ意味で、つまり著作物を複製する権利を独占、独り占めしているのは、著作者であるということです。
逆に言えば、著作者ではない人は、複製(模写)する権利がない、ということが法による原則となります。
先述のとおり、模写も複製であれば、模写することができるのは著作者だけですので、著作者以外の人が模写をした場合は、著作者が有する権利(複製権)を侵害している状態になります。あくまでこれが原則です。
私的使用のための模写ならOK
模写できるのは著作者だけ、というのは原則ですが、原則があるということは、例外もあります。
例外は法でいくつか定められていますが、模写において関係してくるのが「私的使用のための複製」(法30条)です。
条文の柱書のみ抜粋します。
(私的使用のための複製)
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
この条項により、先述の原則に対する例外として、個人的または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とするときは複製することができるとされています。
特に模写というのは自身の技術向上のために行う場合が多いと考えられるため、基本的に「個人的に使用することを目的」としていると考えられますので、作者(※この記事では著作者・著作権者を指すものとします)ではない人であっても、また作者からの複製許諾のない状況であっても、著作権を侵害することなく模写をすることができます。
ネットにアップは侵害とみなされる
インターネットのない時代であれば、ここまでの説明で終わっても良かったのかもしれませんが、ネット時代の昨今では、もう1つ重要な点を考えなければなりません。
それが、複製物の目的外使用です。
先述の法30条1項では、著作物を複製することができる例外を定めていますが、例外扱いされているのは”複製”行為だけ、つまり「模写という行為を完了するところまで」です。
模写によって生み出された複製物については、自由に利用できるものではありません。
「自分で描いたものだから、自分が自由に利用できる」と考えてしまうかもしれませんが、たとえ自分が描いたものであっても、それを自身のSNSなどネットにアップしてしまうと、基本的に複製権の侵害となります。
それを規定しているのが法49条1項1号で、原則(←著作者のみ)の例外(←私的使用ならOK)の例外(←でもネットにアップはNG)という複雑な構成ではありますが、イメージとしては法30条1項による無許諾利用が取り消されるようなものです。
つまり、この条項により複製を行ったとみなされることから、作者からの許諾がある場合や他の権利制限規定(引用など)の適用を受ける場合を除き、複製権の侵害ということになります。
親告罪であることは関係ない
模写した絵画、イラストなどネットにアップしている場合において、「著作権侵害は親告罪だから、権利者から何も言われなければ違法ではない」と考えている方も多いようです。
確かに著作権侵害の多くは親告罪、つまり作者からの告訴がない限り起訴できない犯罪とされていますが、ただ気をつけなければならないのが、親告罪というのはあくまで刑事罰を課すかどうかの手続きにおいて影響するものであり、著作権を侵害しているかしていないかを決定付けるものではありません。
つまり、作者がOKと言わない限り、模写した絵画・イラストをネットにアップする行為は著作権者の複製権を侵害している状況、つまり法21条の規定に違反している違法な状態であるということです。
その”違法な状態”に対して、罰を与えたい、損害賠償を請求したいとして行動を起こすのか、あるいは利用を認めて違法状態を解消するのか、このような判断が作者に委ねられているのです。
自分の向上のために利用しよう
このように、基本的には模写をするのは著作権侵害には当たらず、自由に行うことができます。
ただし、模写によって生まれた絵画やイラストをネットにアップしたりするのは、複製権の侵害とみなされる場合があります。
自己研鑽という模写の本来の目的をしっかり理解して、他人の著作物を正しく利用するようにしましょう。