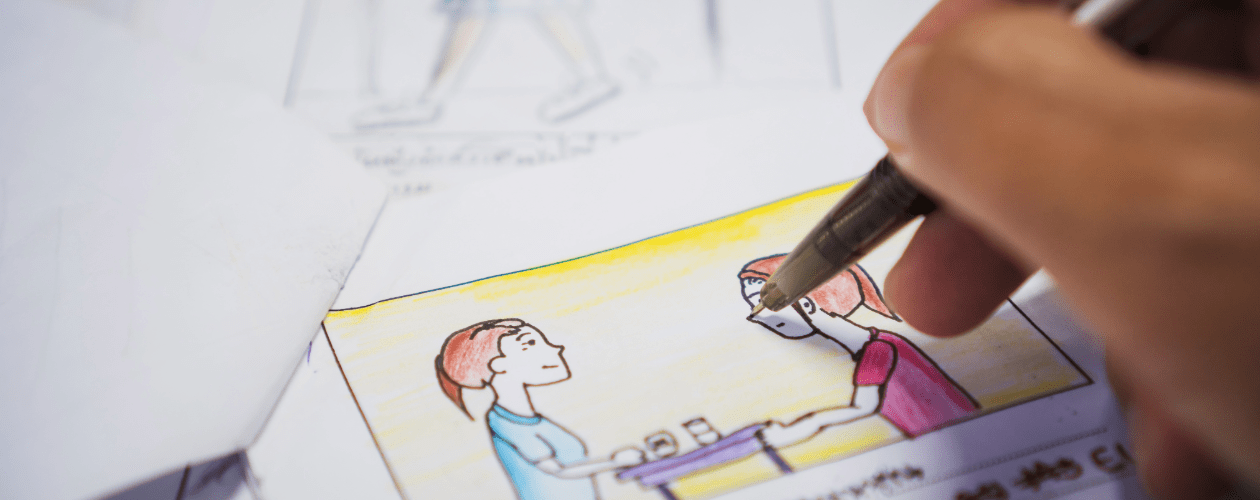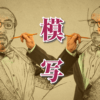SNSなどでたびたび話題になる「トレパク」ですが、他人の作品に対して安易にトレパクしていると断じる、あるいは疑いを投げかけることは勧められる行為ではありません。
その理由を著作権法と裁判例から考えてみます。
トレパクとは?
そもそもトレパクとはどのような意味でしょうか。
明確な定義があるとは言えないと思いますが、通常、「トレス」、つまり他人のイラストなど著作物を描き写すことでその絵柄を「パクる」行為であると認識されているかと思います。
模写・トレス(トレース)に関する著作権の考え方については別の記事で触れていますが、基本的にはネットなどに投稿せず個人で楽しむ分には権利侵害にはなりませんが、ネットにアップしたりする場合に権利侵害に該当する可能性が高まります。
これはあくまで元の絵をそのまま模写した場合ですが、トレパクとして話題になることが多いのは、別の記事で触れたような全く同一の絵を模写・トレスする場合ではなく、元の絵の表情やポーズ、輪郭線などの一部分が特定の別作品と一致または著しく類似しているようなケースであるように感じられます。
いずれにせよ、トレパクという言葉は、単にトレスだけではなくパクるという言葉が付いていることで、まるで著作権侵害をしている前提の悪いイメージを印象付けるものだと言えます。
トレパク=著作権侵害、とは限らない
まず知っておかなければならないのが、仮に輪郭線が一致したとしても、さらに言えば実際にトレスが行われたとしても、それが直ちに著作権侵害になるものではない、ということです。
トレパクはすべて犯罪だと考えている方も少なくないようですが、その認識は正しくありません。
著作権侵害ではないと判断される場合、通常、法的には問題がないという意味です。
つまり、法的に問題のない事項に対しての批判というのは、各自の思想やマナーとして考えているような、明確な基準が存在しない、また社会的合意の取れていない”個人的な考え”に基づくだけのものであるため、決して他人を糾弾できるような材料にはなりません。
トレパクに該当する行為であっても、それが直ちに著作権侵害であるとは言えない。これだけはしっかり認識しておく必要があります。
偶然の一致は著作権侵害ではない
トレパクであっても著作権侵害ではないということに関して、よく誤解されがちな点を2つ挙げてみます。
まず1つ目は、仮に部分的な輪郭線が一致したとしても、それが「偶然の一致」である場合です。
例えば人物を描く場合、一般的には現実に存在する”人間”を元にして顔や腕、足などを描くと思います。つまり、顔には2つの目と鼻、口があり、また腕の先には指が5本描かれることになります。そして、これらの形は、真四角や三角ではなく、人間に存在する実際のパーツに似た形として描かれますし、鼻の下には目ではなく口が描かれます。
「そんなの当たり前だろ」と思うかもしれません。
そう、その当たり前であるために、誰もが「目」「鼻」「口」そして人物の顔だとわかるように描く必要があるわけで、そうなると実在する目や鼻から逸脱しないよう、その形状には必ず制約が生まれます。つまり、表現の幅が狭いわけです。
また、人物である以上、目や鼻の大きさ、腕と手・指のバランス、そしてそれらの可動域から考えて動かすことができる方向や位置などにも制約がありますので、これらの制約も表現の幅を狭める要因になります。
それらに加えて、イラストのジャンルによっては定番的な表現も存在し、例えばいわゆる女性向けゲームのイケメンキャラなら実際の人間よりも顎がシャープに描かれることが多いと言えるのではないでしょうか。
このような制約や定番表現を意識的または無意識に表現することで、偶然に既存の著作物に一致または著しく類似してしまうことは十分起こりえます。
これが仮に著作権侵害の要件の1つである「類似性」を満たしたとしても、偶然である以上「依拠性」は満たさないため、著作権侵害ではないと考えられることになります。
ありふれた表現が一致しても著作権侵害ではない
2つ目として、偶然ではなく、意図的に既存著作物の一部分をトレスした場合です。
この場合は「依拠性」を満たすため、著作権侵害だと判断される可能性は高まりますが、ただ断定はできません。
その理由は、創作的ではない表現、ありふれた表現の一致は著作権侵害ではないと判断される場合が多いためです。
これは先述の制約や定番表現にも関係しますが、表現の幅が狭いということは、意図せず表現が一致してしまう可能性が高くなります。
このような場合でも権利侵害と認定してしまうと自由な創作活動をかなり制限してしまいますし、そもそも例えば「目」の形というのは人間の目を元にしたものですので、特定の創作者が独自に創作したものではなく、その表現を独占できるものではありません。
また、著作権侵害の要件である類似性を満たしているかどうかの判断は難しいのですが、過去の最高裁判断により「表現の本質的特徴を直接感得することができる」場合を類似と考えるようになっているため(「江差追分事件」最判H13.6.28)、仮にトレスすることで輪郭線が部分的に一致したとしても、元のイラストの本質的特徴と言えるような創作的な表現を直接感じ取ることができないのであれば、それは類似していないとして著作権侵害ではないと考えられます。
よって、トレスの有無に関わらず、輪郭の一部が一致しているだけでは著作権侵害だとは言えない場合も多いのです。
元絵の作者自身であっても著作権侵害だと断定できない
昨今のSNSでのトラブル事例を見ていると、自身のイラストに似ている作品を見つけて「ひょっとしてトレパクでは?」と考えてしまう著作者も少なくないように感じます。
そのように”考える”のは自由なのですが、だからといってすぐに他人の作品をトレパクだと決めつけて何らかの対応を迫るような行動を起こすのは一旦待ったほうが良いと考えられます。
これは、トレパクかどうかに関係なく、著作者であっても著作権侵害であることを確定できないためです。
著作者がどんなに指摘したとしても、裁判により著作権侵害ではないと認められた事例は数多く存在します。
著作権とは著作権法によって定義されているものであり、その侵害か否かはこの法に基づいて裁判所によって判断されます。
そもそもトレパクという言葉自体が悪いイメージを持つ言葉であるため、安易に他人に対して投げかけて良いものではないといえます。
特に、特定の作品に対してトレパクだと決めつけて意図的に拡散しようとすることで、まるで第三者からも攻撃してほしいというような、まるで”私刑”を望むような投稿をする著作者も目にしますし、第三者がこのような発信をすることでエンタメのように楽しんでいる層もあるようです。
トレパクによる著作権侵害の疑いが濃厚で何らかの対応を求めたい場合であっても、それは当事者同士で秘密裏にやるべきことで、第三者を巻き込んで炎上させ、あるいは第三者が率先して追い詰めるような行動は決して望ましいものではありません。
トレパク指摘が名誉毀損と判断された事例も
トレパクの指摘に関して裁判になった事例もあります。
とあるイラストレーターA氏に対し、別のイラストレーター・漫画家のB氏が自身の作品をトレスしたとして指摘し、自身のブログ等でその旨を発信していたため、A氏がB氏に対して名誉毀損の損害賠償請求を提訴しました。
裁判では、トレスされたとするB氏のイラストよりもA氏のイラストのほうが先に作成されていた等もあるほか、単に一部の線が重なっただけではトレスであることは証明できないとして、裁判所はA氏のトレス行為があったとは認められないと判断し、B氏に対して名誉毀損の損害賠償(314万円以上)を命じる判決を出しています(東京地判R5.10.13)。
安易なトレパク批判は避けよう
先述の裁判はA氏の無実が証明された「トレスえん罪」事件となりましたが、B氏によるこのような根拠の乏しい指摘によりA氏の仕事やキャリアに与えた影響は計り知れません。
もちろん、B氏としては自身の作品は大切なものであり、それを他人が無断でトレスして自分の作品として発表したら憤慨するのも理解できます。
しかし、だからといって他人を糾弾するためには、十分な証拠が必要です。
単に線の一部がほぼ一致する、あるいは一部を回転・拡大縮小・縦横比変更することでほぼ一致したというだけでは、先述のとおり偶然の一致もありうることから、十分な証拠とは言えません。
このような根拠の乏しい理由だけでトレパク認定してしまうと、法的な責任を負ってしまうリスクは高まります。
安易なトレパク認定は絶対にやめましょう。