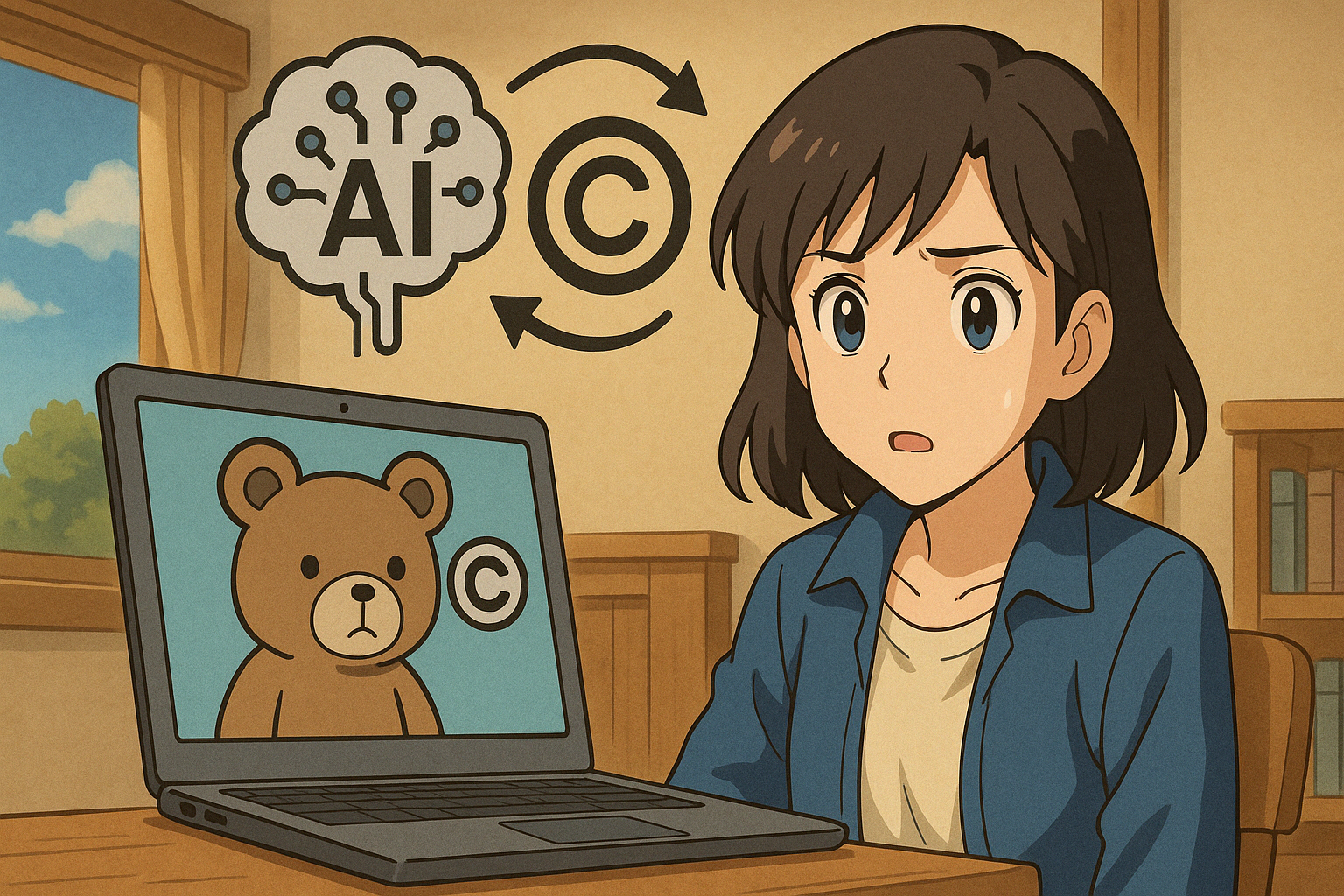AI画像生成ツールの発展により、「ジブリ風」や「ディズニー風」など、既存作品の雰囲気を取り入れた画像を簡単に作れる時代になり、SNSでもそうした画像が数多く投稿されていますし、「ジブリ風」に関しては最近では国会(衆議院内閣委員会)でも話題になるなど、注目を集めています。
ただ、「ジブリ風の画像って著作権的に大丈夫なの?」「違法なのでは?」というような疑問を抱いている方も少なくないようです。
そこで、「ジブリ風」画像の生成が基本的に違法ではない理由を、著作権法の観点から解説します。
「ジブリ風」と「ジブリ作品」は違う
まず大前提として、「ジブリ風」とは、スタジオジブリ作品の中に存在する特定のキャラクターや背景をそのままコピーするものではなく、その画風や世界観を参考にした“雰囲気”の表現です。
「ジブリっぽい」と評価する際の「っぽい」の部分ともいえます。
著作権法で保護される著作物とは、思想又は感情を創作的に「表現」したものであるため、アイデアやスタイルそのものは「表現」ではないため保護の対象外です。
例えば「草原を走る少女」「空飛ぶ乗り物」などの設定や構図は、ジブリ作品にも多く見られますが、それ自体はアイデアであるため著作物ではなく、著作権は発生しません。
つまり、「ジブリ風の雰囲気を感じさせる画像」でも、それがジブリ作品に登場するキャラクターや背景の具体的な表現を複製・改変したものや、既存のジブリ作品に登場するものと創作的な表現が類似したものでない限り、著作権侵害にはなりません。
「アイデアと表現の区別」がなぜ重要か?
先述のとおり、著作権法の基本的な考えとして、「アイデアは自由に使えるが、表現は保護される」という原則があります。
この区別がある理由は、簡単にいえば創作活動の自由を守るためです。
もしアイデアそのものが著作権で保護されると、後から似た発想を思いついた人が同様のテーマで作品を作ることができなくなってしまいます。
たとえば「少女と巨大な不思議な生き物の友情」という物語の骨格は多くの創作物に存在しますが、それは自由に使える発想(アイデア)です。
一方で、映画「となりのトトロ」に登場するトトロの外見やその動き、背景美術などは、スタジオジブリ独自の具体的な表現として保護されます。
この「アイデアと表現の区別」によって、創作における独自性の尊重と、文化の発展を両立することが可能になっているのです。
AI画像生成と著作権法30条の4の関係
AI画像生成に関しては、学習段階で著作物を使用することの合法性がよく問題になります。
これについては、2018年(平成30年)の著作権法改正によって新設(※)された第30条の4によりルールが定められました。
第30条の4(著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用)
著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない(以下略)【概要】
著作物を、AIの学習やデータ分析など享受を目的としない方法で利用する場合は、原則として著作権者の許諾なしに利用が可能。
つまり、AIが「ジブリ風の画風」を学習していたとしても、その学習行為自体は享受(鑑賞・鑑賞のための再利用)を目的としないため、原則として合法ということになります(※著作権者の利益を不当に害する場合や、享受目的が併存する場合、類似物を生成することを目的として学習させる場合などを除く)。
※「享受目的」について注意が必要なのが、あくまで学習段階において、学習するために利用する著作物(条文では「当該著作物」)の創作的な表現を、学習を実施するときに自己が享受し、又は他人に享受させる目的があるか、という点です。基本的に「AI生成物が他人に享受されるか」ということではありません。
さらに、生成された画像そのものから、スタジオジブリが創作した特定の作品における特徴的かつ具体的な表現(=本質的な特徴)を感じ取ることができないのであれば、その出力結果も著作権侵害にはあたらないと解釈するのが基本です。
逆に言えば、ジブリ作品と類似性のあるものを利用する行為は著作権侵害となる可能性が高いです。
ただし誤認を招く表示や利用には注意
「ジブリ風」画像の生成・公開は基本的に問題ないといえますが、例えばジブリ公式の作品であると誤認させる表現や、商標的使用(※商品やサービスの出所を識別する目的での使用)などは注意が必要です。
こうした行為は、著作権だけでなく商標権の侵害や不正競争防止法に違反するリスクがあります。特に営利目的での利用に際しては、表示や文言に十分注意しましょう。
「ジブリ風」は創作の自由の範囲内
結論として、「ジブリ風」の画像をAIで生成することは、著作権法上、違法ではないケースがほとんどです。
だからこそ、生成AIの存在自体は否定すべきではないと考えます。
とはいえ、ジブリ作品を大切に思うファンや、制作者側の視点からすれば、「ジブリ風」という表現を他者が自由に使うことに対して複雑な気持ちを抱く方もいるかもしれません。敬意をもって扱うことは、クリエイターとしての基本的なマナーです。
その一方で、日本の著作権法は第1条で「文化の発展に寄与すること」を目的として掲げています。これは、著作物を保護することで創作意欲やインセンティブを守ると同時に、過度な制限によって新しい表現や二次的な創作が萎縮しないようにするためのバランスでもあります。
つまり、「ジブリ風」のような雰囲気を取り入れた創作が自由に行えることは、文化の多様性や創作活動の活性化につながる、社会的に意義のあることでもあるのです。
AI時代における表現のあり方はまだ模索の途中にありますが、一概に「合法だ!」「いや違法だ!」と争うのでは無く、法のルールと創作の倫理、その両方に目を向けることで、より豊かな創作文化が築かれていくことが望ましいと言えるのではないでしょうか。
”特定のアニメの画風を指示した画像生成は違法なのか?知っておくべきAIと著作権の基本”というタイトルのブログ記事で利用するアイキャッチ画像を、以下の条件で作成してください。
・サイズ:1200px x 400px
・文字ではなく画像で作成
・アニメ風の画風で