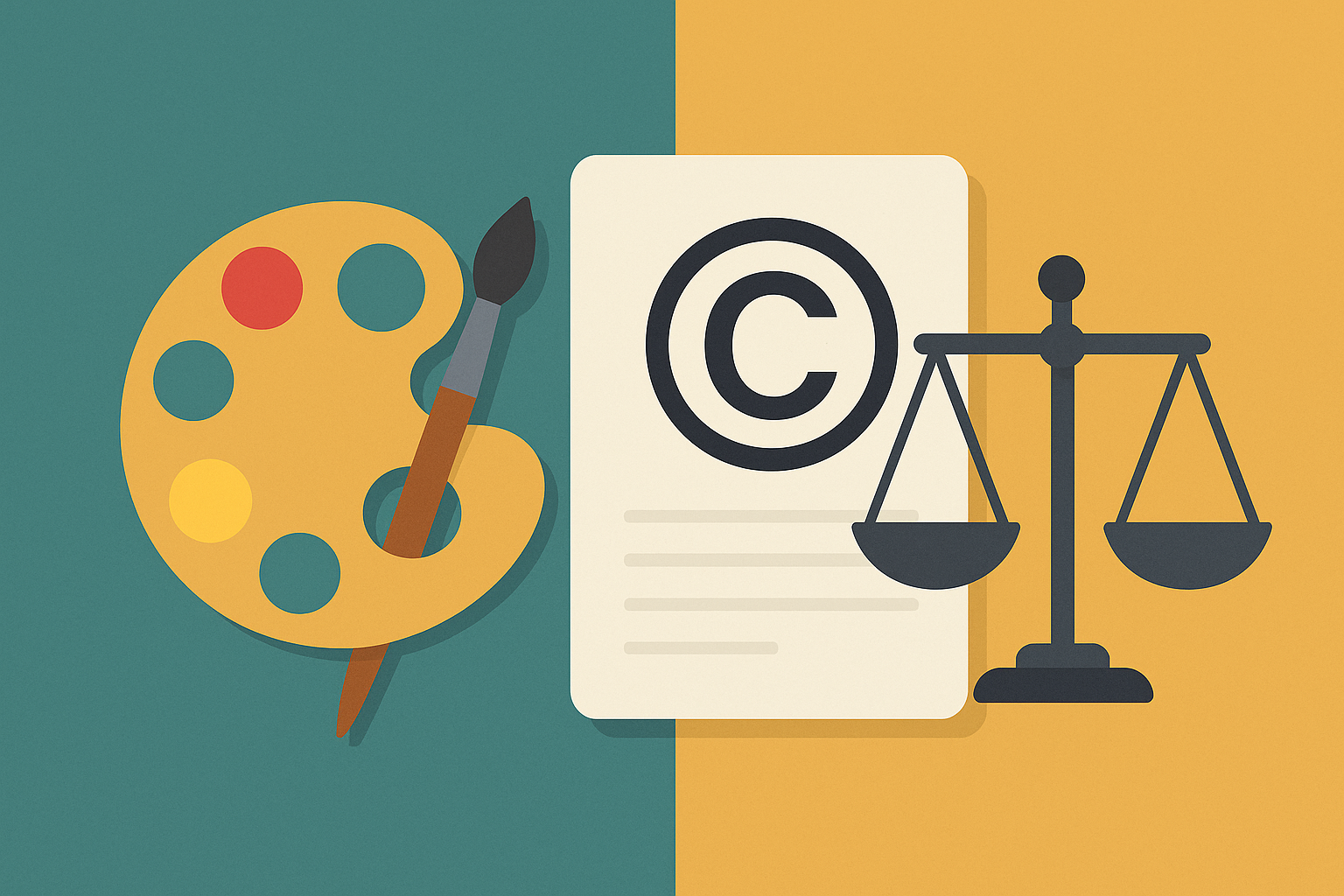私たちは普段、音楽、映画、書籍、写真、イラスト、ウェブ記事など、さまざまな「著作物」に囲まれて生活しています。
そしてそれらは著作権法(以下「法」)により、著作物を創作した著作者や、その著作者から権利を譲り受けた著作権者に対して「著作権」や「著作者人格権」などの専有権を与え、保護しています。
しかし、著作権はしばしば「絶対的な権利」と誤解されがちです。
SNSを見ていると、「著作者が『使うな』と言えば、どんな状況でも一切使えない」と思い込んでいる人も多いように感じます。
これは誤りで、実際には、著作権は著作者が全面的・無制限に支配できる権利ではありません。
その一例として、法律上、著作者の権利が制限される「権利制限規定」という仕組みが挙げられます。
この仕組みによって、法で定める一定の条件を満たす場合には、著作者の許諾がなくても著作物を利用することが認められています。
この記事では、著作権の「絶対性」という誤解を解き、権利制限規定の基本的な考え方や、著作者の意向との関係、さらには著作権制度の目的について考えてみます。
そもそも”著作権”とは何か
著作権の絶対性について考えるにあたって、著作権とはそもそも何なのかをおさらいしておくことが重要です。
著作権とは、著作物を創作した著作者だけが持つ権利で、複製、上映、公衆送信、展示、譲渡、翻案などの利用を原則として独占できる(専有)ものです。
この権利により、著作者は著作物の利用を許諾したり権利を譲渡することによって、自身の著作物から適正な対価を得たり、人格的な価値を守ったりすることができます。
ここで重要なのは、法は著作物やレコードなどが「文化的所産」であることを前提としている点です。これは法1条からもわかります。(※太字は筆者によるもの)
(目的)
第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。
つまり、著作物は単なる個人の所有物ではなく、人類共通の文化の中で生まれ、共有され、発展していくべきものだという思想が根底にあります。
そのため、著作権制度は個人の権利だけでなく、社会全体の文化的利益や発展にも目を向けて設計されています。
権利制限規定とは何か
権利制限規定とは、著作物の利用について、著作権者の許諾が不要とされる例外規定です。
法30条以下に列挙されており、次のような場合が代表例です。
- 私的使用のための複製(30条)
家庭内や個人的な範囲での利用(例:自分用に音楽をCDからスマホにコピー)であれば、著作権者の許諾は不要。 - 引用(32条)
論文、評論、批評などで正当な範囲内で著作物を引用する場合、著作権者の許諾は不要。 - 学校教育のための複製等(35条)
授業で必要な場合、教員や生徒が著作物を複製することができる。 - 視覚・聴覚障害者のための複製等(37条など)
視覚障害者向けに点字化したり、聴覚障害者のために音声を文字起こしする場合は、著作権者の許諾は不要。
これらの権利制限規定は、著作物の円滑な流通や社会的な価値の実現を促進するために存在しています。
つまり、著作権法は著作者の権利保護だけでなく、利用者側の正当な利益や公共の利益を考慮して設計されているのです。
同様に、裁定制度や未管理著作物裁定制度といった強制許諾制度も”利用”を考慮したものであるといえます
著作者の意向と権利制限の関係
権利制限規定の重要な特徴は、「著作者の意向に関係なく適用される」という点です。
例えば、著作者が「自分の作品を授業で使わないでほしい」と望んだとしても、授業での適法な複製についてはその意向は効力を持ちませんし、著作者が「引用を禁止したい」と考えていても、引用に関する法および判例上の要件を満たせば、法的には引用利用が許容されます。
ただし、ここで誤解してはいけないのは、著作者の意向がまったく無意味だということではないという点です。
例えば、著作者が「なるべく引用しないでください」と表明していれば、法的には引用が可能でも、利用者側の判断や倫理には影響を与える可能性があります。
特に商業利用や繊細なテーマを扱う場合、法の許容範囲に甘えすぎず、著作者の意向や感情を尊重する姿勢が求められます。
著作権法の本質は「バランス」にある
著作権制度の目的は、単に権利者を保護することではありません。先述した法1条にもあるとおり、法の目的が「著作物の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与すること」と明記されています。
著作物やレコード、放送などが「文化的所産」であるという前提のもと、社会における自由な利用と創作の保護のバランスを取ることが、法が求める著作権制度の根幹であるといえます。
そのため、権利制限規定は単なる「例外」ではなく、制度全体を支える重要な柱です。
特に教育・研究分野、報道、障害者支援などは、社会の知的・文化的基盤を支える活動であり、また表現の自由との関係からも、法はこうした活動を妨げないよう配慮されています。
法の範囲と倫理のバランスを意識する
著作権は、原則として著作物の創作時から始まって著作者の死後70年間も保護されるという点で非常に強力な権利ではありますが、決して絶対的なものではありません。
法律上は、権利制限規定に該当する利用であれば、著作者の許諾や意向に関係なく適法に利用できます。
しかし、だからといって著作者の意向や気持ちを軽視して良いわけではありません。
法的に許されていても、無用な対立やトラブルを避けるためには、倫理的な配慮や事前の相談が求められる場面もあります。
著作権制度は、「権利者を守る盾」であると同時に、「利用者の自由を保障する橋」でもあります。
そしてその前提には、著作物やレコードといった創作物が文化的所産であるという考え方があります。
文化の発展に資する公正な利用を推進するためにも、法律の許容範囲を正しく理解しつつ、関係者間の健全なコミュニケーションを心がけたいものです。